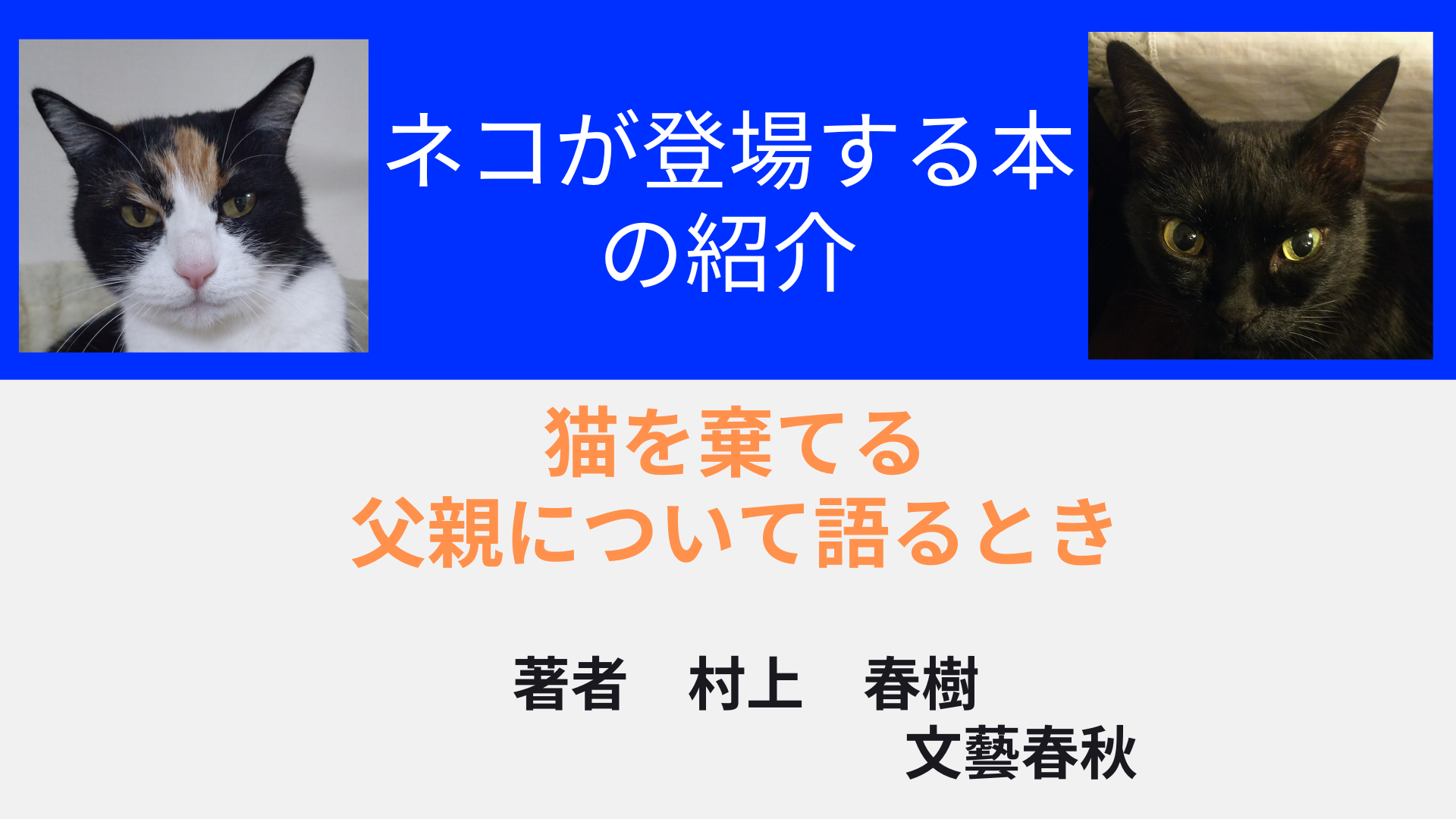この本の中で猫が書かれているのは始めと終わり。
始めは、題名の通り猫を棄てに行く場面。
昭和30年代の始め、
「ともあれ父とぼくはある夏の午後、海岸に雌猫を棄てに行った」p.15
「とにかく父とぼくは香櫨園の浜に猫をおいて、さよならを言い、自転車でうちに帰ってきた」p.15
「かわいそうやけど、まあしょうがなかったもんな」という感じで玄関の戸をがらりと開けると、さっき棄ててきたはずの猫が『にゃあ』といって尻尾立てて愛想良く僕らを出迎えた。先回りして、とっくに家に帰っていたのだ」p.16
「そのときの父の呆然とした顔をよく覚えている。でもその呆然とした顔は、やがて感心した表情に変わり、そして最後にはいくらかほっとした顔になった。そして結局それからもその猫を飼い続けることになった」p.16
「うちにはいつも猫がいた」p.17
「兄弟を持たなかったので、猫と本が僕の一番の大事な仲間だった」p.17
「なのにどうしてその猫を海辺に棄てにいかなければならなかったのだろう?」p.17
「なぜ僕はそのことに対して異議を唱えなかっただろう?」p.17
「今でも僕にとってひとつの謎になっている」pp.17-18
そして、終わりに書かれているのは飼い猫との別れの経緯。
当時飼っていた可愛くて毛並みのいい白い子猫が、庭にあった立派な松の木をするすると登っていった。
「まるで自分の勇敢さ、機敏さを僕に自慢するみたいに」pp.109-110
やがて枝の中に消えてしまった猫は、降りられなくなったのか、助けを求めるように情けない声で鳴き始めた。
「猫は木を上がるのは上手だが、降りるのは不得意だ」p.110
何とか助けたいと思って父親を呼んだが手の打ちようがない。
結局、その後、子猫は「夜のうちに下になんとか降りてきて、そのままどこかに行ってしまったのかもしれない(どこに?)」p.111
降りられないまま衰弱して死んでしまったのか?
今となっては、仔猫がどうなったのかわからないままになった。
「それが僕の子供時代の、猫にまつわるもうひとつの印象的な思い出だ」と振り返っている。
言うまでもなく、猫にまつわる一つ目の思い出が、猫を棄てにいったこと。
二つ目の思い出が子猫との未だ納得できない?別れである。
その思い出に挟まるように、この本の大半が父親のことを書いている。
村上さんの父は戦中派で実際に中国の南京へ出征の後も二度戦地に行っている。
戦地で過酷な人の生き死を見てきている。
終戦後、毎朝、父親が箱に向かって手を合わせているのは、戦争で亡くなった方への思いであり供養なのか。
高校の教員をしながら唯一趣味にしたのが俳句!
俳句は出征した頃から書いている。
戦地での思い、戦争体験、移り変わる戦後の生活の中での思いを俳句という表現で語っている。
そんな父親が一人っ子である村上さん伝えたかったこととは何なのか。
村上さんと父親は、特に大人になってから決して仲のいい親子ではなかった。
むしろ疎遠になり、父親の死に立ち会っている。
そして、村上さん自身が晩年にさしかかった今、「猫を捨てる(父親について語るとき)」を書いている。
私事であるが、私の父も大正9年に生まれ、中国に出征している。
父は字が上手で「戦地で戦友の代筆をしたり文章を書いたりしたことで激戦地に行くことがなく、結果として生きて戻ることができた」と聞いたことがある。
父の兄はグアム島で戦死している。
仕事の傍ら遺族会の仕事、戦没者慰霊碑の建立等に尽力していた父の姿を思い出す。
村上さんは、何故、「猫を捨てる(父親について語るとき)」を書いたのか?
「猫を棄てる」が主題で、「父親について語るとき」を副題にしたのか?
「猫への思いを共有する出来事を語る中で父親のことを語っている」
「父親の生き様を通して、戦争を知らない村上さんが戦争と向き合ってきた」
それぐらいにしか私には思いつかない。
何かもっと深い意味があるのだと思うが、今の私には言語で表すことができない。
最後に、私にとってキーワードになる文章を引用し、「猫を捨てる(父親について語るとき)」の紹介を終えたい。
「僕はひとりの平凡な人間の、ひとりの平凡な息子に過ぎないという事実だ」p.114
「我々は結局のところ、偶然がたまたま生んだひとつの事実を、唯一無二の事実とみなして生きているだけのことなのではあるまいか」p.114
「言い換えれば我々は、広大な大地に向けて降る膨大な数の雨粒の名もなき一滴に過ぎない」p.115
「一滴の雨水には、一滴の雨水なりの思いがある」p.115
「一滴の雨水の歴史があり、それを受け継いでいくという一滴の雨水の責務がある。我々はそれを忘れてはならないだろう」p.115
<あとがき「小さな歴史のかけら」から>
「メッセージとして書きたくなかった」p.120
「歴史の片隅にあるひとつの名もなき物語として、できるだけそのままの形で提示したかっただけだ」pp.120-121
「そしてかつて僕のそばにいた何匹かの猫たちが、その物語の流れを裏側からそっと支えてくれた」p.121
<追伸>
※「猫を捨てる(父親について語るとき)」に描かれている絵が素晴らしい!
「いつも生活の中に猫がいた」と語っている当時の村上さんの生活が伝わってくる。
台湾のイラストレーター「高妍」さんの絵に引き込まれた。